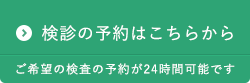いつまでも残る咳には要注意

咳はどうして出るのでしょう。
呼吸によって鼻や口から取り込まれた空気は、のどから気管・気管支を通って肺に到達します。この空気の通り道(気道)のどこかに異常があると、体に異常を排除する動きが起こります。これが咳(咳嗽/がいそう)です。
咳がでる主な原因は次の通りです。
①空気に原因がある場合
- 空気中の塵・埃などの有害な物質は、気道の粘膜に捕らえられて、痰として排出されます。この痰を出すために、咳が出ます。咳払いや、むせたりした時のせきこみも、これにあたります。
②気道に異常が起きている場合
- 風邪などで気道の粘膜が炎症を起こすと、病原体とそれに感染した粘膜を痰として排除します。また、ぜんそく発作などで、のどの粘膜が敏感になっている時も咳が出やすくなっています。
③体の異常を上手く検知出来ない場合
- 気道の異常を感知する仕組みが過剰反応した時や、心因性ストレス・特定の降圧薬の副作用によっても咳が出ます。
この時は痰を伴わない乾性咳(空咳)が多くなります。 ④肺に病変がある場合
- 肺炎や肺結核、肺がんなどの病変が進行して気管支に及ぶと咳が出るようになります。
咳はその持続期間によって以下の3つに分けられます。
①急性咳嗽:3週間以内
- 原因の多くは上気道炎(かぜ症候群・インフルエンザなど)で、その8~9割がウイルス感染です。上気道炎を起こすウイルスは数十種類もありますが、インフルエンザウイルスを除いて、ウイルスを殺す有効な薬はありません。
十分な休養が一番の薬ですが、必要に応じて咳止め・去痰剤を処方します。
ただし3日以上高熱が続いたり、色のついた鼻水や痰が出る場合や、扁桃腺が腫れているときなどは細菌の二次感染や肺炎が疑われますので、レントゲンでの確認が必要です。 ②遷延性咳嗽:3~8週間
- 熱やのどの痛みは良くなったのに咳だけ残る場合が該当し、のどや気管支の粘膜が、まだ敏感な状態であるためと考えられます。また、マイコプラズマや百日咳のように、咳を特に長引かせる病原体が原因の場合もあります。
症状が強く日常生活に不便がある場合には咳止めを使用しますが、大部分は痰を伴わない空咳で自然に回復します。しかし、肺結核や肺癌・間質性肺炎等が原因の場合もあるので、回復が思わしくない場合は、レントゲン等の検査をご相談ください。 ③慢性咳嗽:8週間以上
- 頻度は少ないですがその原因は多彩で、咳喘息・アトピー咳嗽・副鼻腔気管支症候群・喫煙による慢性気管支炎など、気道に原因のあるものや、逆流性食道炎など一見関係のなさそうなものの場合もあります。治療は原因により異なり、専門的な診断が必要ですので、受診の上ご相談ください。
胸の痛みが続くとき

1.心臓疾患
胸痛の原因となる主な心臓疾患は狭心症と心筋梗塞です。これらの疾患は、心筋に酸素を送る血管(冠状動脈)が、動脈硬化などの原因で狭くなり、心筋が酸欠になることで生じます。
①狭心症
冠状動脈が狭くなり、一時的に心筋が酸欠になる状態を言います。
(1)痛み
- 発作的に前胸〜左胸が痛くなります。圧迫感・灼熱感・締め付けられる感じ、と表現される場合もあります。多くは数分程度でおさまります。
-
(2)種類
-
- 労作性狭心症…労作時(体を動かしている時)や興奮した時に発生します。
- 安静時狭心症…就眠中(特に朝方)に発生します。冠れん縮性狭心症ともいいます。
- 不安定狭心症…労作時や安静時を問わず狭心症発作の頻度が増えた状態です。
(3)治療方法
- まず安静にして体の緊張をとります。
冠状動脈を広げるためにニトロ製剤等が使われますが、狭心症は発作を繰り返して心筋梗塞に移行することが多いため、反復する胸の痛みを自覚した場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
②心筋梗塞
冠状動脈が完全に詰まり、心筋が壊死してしまう状態が心筋梗塞です。
心臓のポンプ機能が失われ、全身に血液を送れなくなり最悪の場合死に至ります。
狭心症が前触れになっていることが多いですが、突然発症する場合もあります。
(1)痛み
- 多くは狭心症の時の痛みより激しく、冷や汗・吐き気・おう吐を伴なうこともあります。ニトロ製剤はあまり効果はありません。
(2)心筋梗塞!?と思ったら
- 心筋梗塞では、いかに早く設備の整った医療機関で治療を始めるかが生死の分かれ目になります。
胸の痛み・動悸・息苦しさなどの症状が突然発生した場合は、直ちに医療機関にご相談頂き、それが困難な場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
2.気胸(自然気胸)…やせ型の体型の方はご用心
肺の表面に穴が空くと、空気が肺と肋骨の間に漏れて(これを「肺虚脱」と言います。)肺がしぼんでしまいます。この状態を気胸と呼んでいます。気胸のうち、外傷などのはっきりした原因がない状況で生じる気胸を自然気胸といいます。
自然気胸の原因は良く分かっていませんが、統計的には、若いやせ型の男性に多く発生するとされています。
通常左右どちらかの肺に突然発症し、肺虚脱の程度によって胸痛・息切れ・呼吸困難などの症状がありますが、両肺同時に発症することはまれです。
診断は胸部レントゲンでほぼ100%つきます。
肺虚脱の程度が軽ければ数日の安静で、肺の表面にあいた穴は自然に閉じます。
穴が閉じれば1週間程度で症状は改善します。
ある程度以上肺虚脱が進行すると、穴が自然に閉じるのが難しくなります。こうなると、肺の外にたまった空気を体の外に出す処置が必要で、入院が必要な場合も出てきます。
自然気胸は再発率が約15%あり、再発時に前回と同じ処置をすると約半数で再々発するとされています。このため再発時には穴の空いているところを外科的に縫い合わせる、もしくは穴の空いた弱い部分だけ切除するといった様な方法を取る事になります。
気胸は突然の胸の痛みをきたす疾患ですが、適切に診断し処置をすれば命に関わる病気ではありません。しかし、放置すると回復が遅れる場合がありますので、気になった場合は早めに医療機関を受診しましょう。
3.肋骨の骨折…こんなことでも肋骨は折れます
肋骨は左右の胸に12本ずつあり、後ろは背骨と、前は軟骨をはさんで胸骨と接続して、肺を包んでいます。
上下に隣り合った肋骨は筋肉で結びついており、呼吸の際にこの筋肉が動き、肋骨を通じて肺を動かします。
普段の生活のなかでも、不規則な呼吸や体の態勢の時に、肋骨に異常な圧力が加わると折れたりヒビが入ったりする場合があります。
例えば…①風邪をひいて咳がつづいていた ②大きなくしゃみをした ③急に体をひねった ④長時間、体をひねって何かを見上げていた
こうしたきっかけの後に、肋骨(外から押さえて硬いところです)のどこかで、ピンポイントに近い形で痛みが出てきた時は肋骨骨折の可能性があります。酷くなると、肋骨が動くたびに痛みが出るようになり、十分に呼吸ができなくなったりします。
肋骨は絶えず動いて肺を動かさなければならないので、他の骨折の様にギプス等で固定する(=動かなくする)ことはできません。肋骨が自然にくっつくのを待つのが主な治療方法ですが、そのためには痛みのコントロールが必要です。
- 激しい運動を控える
- 大声や大笑い、突然叫んだりすることを控える
- 咳止め、感冒薬等で咳、くしゃみを減らす
それでも痛みが強いときには、特殊な装具(肋骨バンド・バストバンド)を使って肋骨の動きを部分的に制限します。以前は整形外科で装着してもらっていましたが、最近はドラッグストア等でも購入できます。
一般的に、痛みが落ち着くまで約2~3週間、完全に骨がくっつくまで2ヶ月程度とされています。肋骨骨折はレントゲンを撮ってもわからないことも多く、診察によって痛い場所と痛みの性質を特定することが重要な診断の手がかりとなります。胸の痛みが改善せず、上記のきっかけなどに心当たりがある場合は遠慮なくご相談ください。
その腰痛は、”石”かも(尿路結石)

椎間板ヘルニア、ぎっくり腰、腰椎圧迫骨折…、一般的に腰の痛みは背骨が関係していることが多いですが、背中~腰、下腹部の痛みの場合、腎臓・尿管結石も考える必要があります。
特に左右どちらかに偏った、突然襲ってくる痛みは要注意です。
腎臓は、血液中の不要となった物質を尿として排出する働きをしていますが、なんらかの原因で、尿中の物質が腎臓の中で結晶を作り結石になる事があります。通常、結石が腎臓にあるうちは痛みはあまり感じません。 結石が、腎臓からこぼれて尿管を通る時に尿管の狭いところに引っかかり、尿の流れが詰まったり尿管の内側が結石で傷つくと、激痛を発するようになります。
痛みのほかに、尿意はあるのに尿が出にくい・出ない、尿に血が混じる、などの症状や、吐き気・嘔吐・微熱などもあり、時間とともに痛い場所が下方に移動することもあります。
方法としては、
- 尿管の緊張を取る薬を使用する。
- 点滴で水分を補給して、尿量を増やして結石が流れやすくする。
などがあります。
尿管結石は、直径5mm程度なら尿管に石が入っても痛みをほとんど感じないことも珍しくありません。ですから健診等で小さな石が腎臓に見つかっても、痛みがなければ当面治療は必要ありません。
しかし、尿管にこぼれると非常に強い痛みが出る事もあるので、痛みその他上記の症状が出た場合には、速やかに泌尿器科(程度が酷い場合は救急病院)を受診下さい。
- 偏食が多い。一度に多く食べる。(特に夕食)
- 動物性蛋白、砂糖、脂肪分の摂取量が多く野菜や海藻類が不足しがちである。
- 水分の摂取量が少ない。
- 環境因子(暑くて発汗)が影響。
- ストレスが多い。
また、結石の大半はシュウ酸カルシウムが成分となっており、シュウ酸の摂取を抑えることが結石の予防につながることがわかってきています。結石(特にシュウ酸カルシウム結石)を防ぐには、次の点に注意しましょう。
①水分摂取について
食事以外で1日2Lの水分とるように心がけましょう。ただしお茶類でとる場合には、シュウ酸を多く含む玉露や紅茶は避け、番茶や麦茶、ほうじ茶といったシュウ酸の少ないものにしましょう。ウーロン茶は種類によってシュウ酸を多く含むものがあるので、たくさん飲むのは避けたほうが無難です。
糖分や塩分の多いコーヒー、コーラ、ジュースなども摂り過ぎないようにしましょう。
②カルシウムについて
カルシウムは控えたほうがよいと思われがちですがその逆で、食品等で摂取したカルシウムは腸の中でシュウ酸と結合し、便と一緒にシュウ酸を体外に出す働きをするので、結石予防に役立ちます。
カルシウムは、乳製品、大豆製品、海藻類、小魚などのほか、春菊や小松菜やなどの野菜にもたくさん含まれていますので、1日600mg以上を目安に色々な食品からとるようにしましょう。
③食事
- ホウレンソウは茹でておひたしにすると、シュウ酸を半分程度に減らせます。
- シュウ酸を多く含む食品は、カルシウムと一緒にとるようにしましょう。
以下の組み合わせを参考にして下さい。
- ホウレンソウにカツオ節やちりめじゃこをかける。
- タケノコはワカメと一緒に煮物にする。
- チョコレートはミルク入りを選ぶか、牛乳と一緒に食べる。
- ココアや紅茶はミルクを入れる。
④日常生活
適度な運動をしましょう。ただし、汗をかいた後は水分を十分に摂るようにしましょう。
十分に睡眠をとり、ストレスをなるべく溜め込まないようにしましょう。
尿路結石を予防するために、こんなことにも心がけを!/ 日本ケミファ
しつこい頭痛。これって…。

だれもが一度は悩まされたことのある頭痛。頭痛は、症状の出方によって次の3種類に大きく分けられます。
1.日常的に起こる頭痛
風邪による発熱や、疲労・二日酔いなどで起こる頭痛です。原因が解消されれば頭痛も改善します。
2.慢性的に起こる頭痛
原因となる病気、異常がないのに繰り返し起こる頭痛です。頭痛全体の約80%を占めるとされています。大きく次の3つに分けられます。
①緊張型頭痛
ストレスや緊張、無理な姿勢などが原因と考えられる頭痛で、子供から高齢者まで、幅広い年齢層でみられます。
(1)症状
頭が締めつけられるような鈍い痛みが30分以上、時には数日間続きます。
肩や首の強いこり、めまい、全身のだるさなどを伴うこともあります。
(2)治療
時々頭痛が起きる程度なら治療は不要です。頭痛が起きたときは適度に体を動かしたり、ストレッチなどで固まった筋肉の血行を改善しましょう。
痛みが毎日のように続く場合は鎮痛薬等の薬での治療を行う事になりますが、効果は一時的であり、頭痛を根本的に改善するものではないため、予防が大切になります。
(3)予防
緊張型頭痛の予防には、心身のストレスを溜めないようにする事が重要です。
日頃から適度な運動を心がけ、同じ姿勢を続けないように心がけましょう。
入浴時に首や肩をマッサージするのも効果的です。
ウォーキングやストレッチといった軽い運動を習慣化し、のんびりした時間をもつ様にしましょう。
②片頭痛
慢性頭痛の中でも日常生活に一番支障を来す頭痛で、男性よりも女性に多くみられます。10~20歳代で現れ始める事が多く、その後症状を繰り返す様になります。頭痛は数時間から、2~3日間続くこともあります。
(1)症状
約20~30%の人は頭痛が起こる前に前兆が見られます。目の前にチカチカと光るフラッシュのようなものがあらわれ、視野の片側又は中心部が見えにくくなる閃輝暗点(せんきあんてん)と呼ばれる症状や、感覚が鈍くなる感覚異常・言葉が話しにくくなる(失語性言語障害)場合もあります。こうした前兆の多くは15~30分で消失し、続いて頭痛が始まります。
片側のこめかみから目の辺りに脈打つような痛みが現れて約1時間でピークに達します。多くの場合筋肉痛や肩こり、吐き気や嘔吐を伴います。刺激に対し敏感になって、普段は気にならない光や音や臭いを不快に感じたりします。動くと痛みが強くなるため仕事や勉強や家事が出来ず、寝込んでしまう事もあります。
やがて疲労感や眠気が現れ、4~72時間で自然に痛みが消失していきます。
(2)対処方法
発作が起きたときは、光や音の刺激を避けて暗い静かな場所で横になって休みましょう。椅子に座って安静にするだけでも効果があります。軽症の場合は数時間の休養で治ることもあります。痛む部分を冷たいタオルや冷却シートなどで冷やすのも効果があります。
(3)治療
片頭痛の治療には、頭痛発作のときに服用する急性期治療薬や、発作を防ぐ予防薬を使います。様々な薬がありますが、服用のタイミングが難しかったり、気長に容量を調節して服用する必要がありますので、頭痛専門医もしくは頭痛専門外来にご相談ください。
(4)予防
片頭痛は、頭の中で血管が拡がり、大きくなった拍動が血管の周りの神経に刺激となって伝わることで起こるため、過労やストレスから解放された後に発作を起こすケースが多いようです。このため日頃からストレスを溜め込まないようにすることが大切です。
それ以外にも次のような色々な事が原因とされています。出来るだけこれらのことを避けるのが、頭痛の予防につながります。
- 寝過ぎ・寝不足
- 人混みや騒音、まぶしい光、香水などの匂い
- アルコール、チョコレートやチーズ・柑橘類等、食品添加物
- 空腹
- 天候の変化や温度差
③群発頭痛
群発頭痛は20~40歳代の男性に多く、有病率は約1000人に1人です。
季節の変わり目の様な特定の時期に頭痛が始まり、一度痛みが現れると毎日のように頭痛を起こすことから群発頭痛といわれています。
頭痛は約1~数ヵ月続き(群発期間といいます)、半年から2~3年と間をおいて再発しますが、群発期間以外は、頭痛はすっかり治まってしまいます。
(1)症状
片頭痛よりも激しい痛みの場合が多く、数ヶ月間、夜間や睡眠時のほぼ同じ時間に片側の目の奥、上顎やこめかみの片側に現れます。
「目がえぐられるような」「きりで刺されるような」と表現されるような、耐え難い痛みのため、寝ていても痛みが出るとじっとしていられず、痛みを紛らわせるために頭部を叩いたり、壁や柱に頭を打ちつけたり、頭を抱えて部屋中を動き回ります。
眼球結膜充血・流涙・鼻汁・鼻閉なども見られ、15分~3時間ほどの痛みが、1日に1~2回起こります。
(2)治療
- 薬物療法
発作時の治療薬ではスマトリプタン皮下注射が推奨されており、自己注射が認められています。 - 純酸素吸入法
医療用の純度100%の酸素をフェイスマスクを通して毎分7リットルを15分吸入する治療法です。吸入を開始して5分ほどで痛みは軽くなってきます。
発作が起きた時点でできるだけ早く始めるとより効果的です。早急に酸素設備を備えた医療機関を受診しましょう。
(3)予防
アルコールやタバコが頭痛を引き起こすため、飲酒や喫煙を控えましょう。
また、気圧の急激な変化が頭痛を引き起こすこともあります。
登山や飛行機に乗る場合は、医師に相談しましょう。
3.脳の異常に伴う頭痛
頭痛の中には、くも膜下出血や脳出血・感染症(髄膜炎など)・脳腫瘍といった脳の病気によって引き起こされるものがあります。
次のような「いつもと違う頭痛」の場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 今までにない強い頭痛
- 突然の激しい頭痛
- 痛みが急に強くなる
- 回を重ねるごとに痛みが徐々に強くなる
- 発熱を伴う頭痛
- 手足のしびれがある
- けいれんを伴う
- 意識がもうろうとなる
偏頭痛予防薬の効果と副作用
熱中症かも!?

熱中症とは
私たちの体では、じっとしていても心臓や脳など休まず活動している臓器があるため熱が発生しています。普通はこの温度(体温)が上がり過ぎないように、汗をかくなどの体温を調節する仕組みが働いています。しかしこの仕組みが乱れると体温が下がらなくなって、頭痛、めまい、吐き気など多くの症状があらわれます。これが熱中症です。
熱中症になりやすい3つの要因
①環境
それほど高温でなくても注意が必要です。
・気温が高い ・日差しが強い ・急に暑くなった
・熱波の襲来 ・湿度が高い ・風が弱い
・閉め切った部屋 ・エアコンがない部屋
②からだ
体の弱い方、持病のある方は特に注意が必要です。
・高齢者、乳幼児、糖尿病や精神疾患のある方
・下痢、インフルエンザなどの脱水症状のある方
・低栄養状態の方 ・二日酔い、寝不足の方
③行動
・長時間の屋外作業
・水分補給のできない状況 出典:環境省熱中症予防情報サイト
熱中症の症状…こんな症状には特に注意が必要です。
①口がひどく乾く ・めまい、立ちくらみ ・ひどく汗をかく など
→体から水分が失われているサインです。
②体がだるい ・生あくびがでる ・頭痛 ・吐き気、おう吐がある など
→体温の調節ができにくくなってきている可能性があります。
③手足がふるえる ・けいれんする ・体温が高い ・意識がもうろうとする
→体に必要な電解質(ナトリウムなど)が失われ、臓器の機能にも支障が出ています。
出典:日本救急医学会「熱中症に関する委員会」熱中症診療ガイドライン2015環境省熱中症予防情報サイト
対処方法について
意識がない、あるいは呼びかけにはっきり答えない場合はすぐに救急車を呼びましょう。救急車が到着するまでの間、もしくは意識があっても様子がおかしいと気付いたら、次の応急処置を行いましょう。
①涼しい場所に移動しましょう
②からだを冷却しましょう
- 衣服をゆるめて寝かせ、頭より足を高くして休ませるようにします。
- 露出した皮膚に冷水をかけたり、うちわや扇風機などで扇ぎます。
- 氷のうなどがあれば、くび・両脇の下・太ももの付け根の前面など(太い血管のあるところ)に当てて冷やしましょう。
③水分・電解質の補給
自力で水分が取れれば、スポーツドリンク・経口補水液(OS-1) などを飲ませましょう。
出典:症状別の救急処置|大塚製薬熱中症を予防するには
①暑さを避けましょう
- 室内では
室温をこまめに確認しましょう
扇風機やエアコンで室温を調節しましょう - 外出時には
日傘、帽子を着用しましょう
日陰を利用、こまめに休憩をとりましょう
日差しの強い日は日中の外出をなるべく控えましょう
②体調を整えましょう
睡眠、食事など規則正しい生活に心がけ、疲労を溜め込まないようにしましょう。
③水分をこまめに補給しましょう
- 喉の渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分・スポーツドリンク・OS-1などを補給しましょう。
- 通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用しましょう。